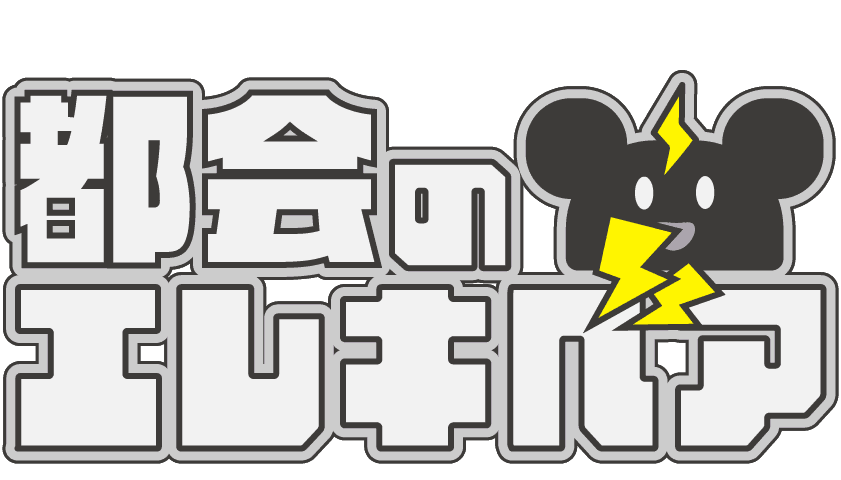- ホーム
- 20221215_01
【書籍紹介】「ゲーム制作者になるための3Dグラフィックス技術」に出てくる用語を簡潔にまとめる
おすすめ技術書グラフィックス
2022-12-15
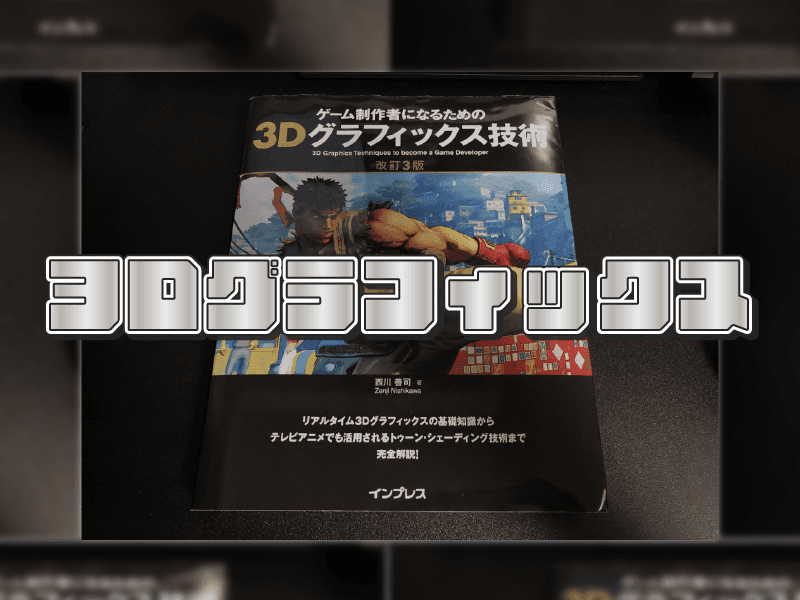
おすすめ技術書グラフィックス
2022-12-15
関連記事

【Unity】第二回 シェーダーライティング入門 〜テクスチャマップを使用したライティング〜(法線マップ、スペキュラマップ、AOマップ)【シェーダー】
2023-03-14

【Unity】第一回 シェーダーライティング入門 〜基本のライティング〜(Lambert、Phong、HalfLambert、Blinn-Phong、リムライト)【シェーダー】
2023-02-28
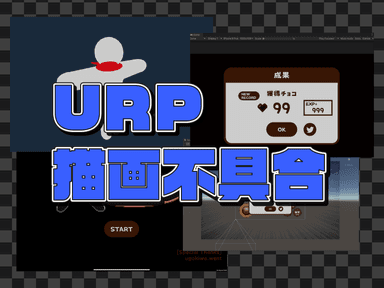
【Unity】URPでシェーダー実装した際に発生した不具合と対処方法まとめ
2023-02-13
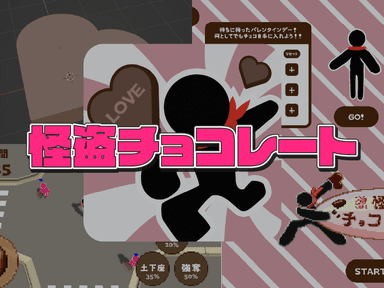
【Unity】「怪盗チョコレート」をリリース!工夫点や反省点をざっと振り返る【バレンタイン】
2023-02-12
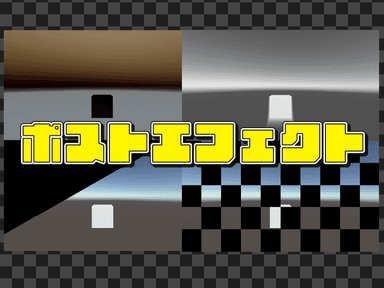
【Unity】ポストエフェクトをシェーダーで実装する(基礎、複数エフェクト適用、描画パス切替)【シェーダー】
2023-01-28
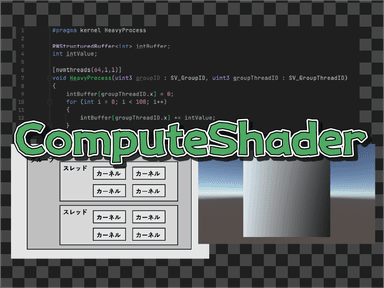
【Unity】ComputeShaderの基本的な使い方についてまとめる
2023-01-07
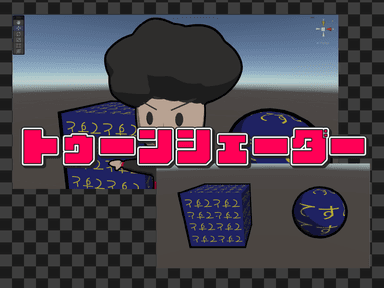
【Unity】トゥーンシェーダーを一から自作する(陰影+輪郭線)【シェーダー】
2023-01-02
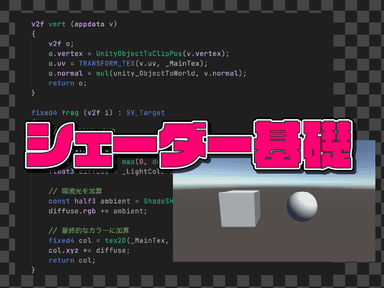
【Unity】Unityシェーダーの基礎とLambert拡散反射の実装【シェーダー】
2022-12-29